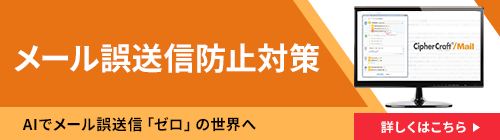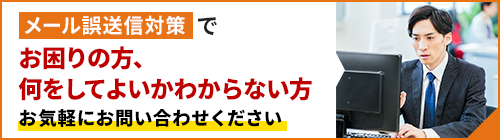ここに本文を書きます。
メールセキュリティのコラム
2025.03.13
メール誤送信の情報漏えいリスクと製品の機能と業者の選び方
メール誤送信の情報漏えいリスクと製品の機能と業者の選び方
メール誤送信による情報漏えいリスクについて
現在日本経済を支えている多くの企業はIT技術を取り入れています。従来では書類として扱っていた情報を全てデータ化した企業も少なくありません。また、クライアントや社員間のやり取りも一昔前は電話やファックスを用いるのが一般的でしたが、現在ではメールサービスが充実しているので、会社でも連絡手段として活用している人は少なくありません。メールを活用することで直接的に話をしなくても相談に乗ることができたり、アドバイスをすることが可能です。また、電話で伝えにくい情報もファイルを添付することで容易に情報共有ができる可能性があります。
このように利便性が高いので活用している企業も多いですが、メールでのやり取りに対して不安を抱いている企業も少なくありません。その不安の一つとして挙げられるのがメール誤送信です。メール誤送信とはメールを送る相手を誤って送信してしまう、または伝える内容を間違えて相手に情報を届けてしまうことです。一般的に誤って送信をした時には、再度メールを送信して間違ってしまった旨を報告、謝罪するのが一般的です。基本的にこのように適切な対応を取ることで相手に不快感を抱かせることは少なくなりますが、既に情報を伝えてしまっているので、情報漏えいリスクに対して懸念する企業は少なくありません。
実際にメールでプロジェクトの内容を話し合う企業も多いです。更に企業の中には資料を添付して送信することもあるので、間違えて送信をすれば多くの情報を漏洩してしまう可能性があります。基本的に悪用する方は少ないですが、もし万が一不特定多数の人に知られれば企業側だけでなく、共同でプロジェクトを進めている企業などにも迷惑をかけてしまう恐れがあります。
企業の運営者の中には重要なデータのやり取りやプロジェクトの内容に関する話し合いに関しては電話で行うことを検討している人も少なくありませんが、既にメールは企業間のやり取りにはおいては不可欠なツールとなりつつあるので、メールでの連絡を少なくする、できる限り利用しないようにすると企業とのやり取りがスムーズに行うことができない可能性があります。そのため、メールを使い続けたいと考えている企業の中には情報漏えいリスクなどを減らす目的でメール誤送信をできるだけ少なくできる製品の導入をしているところがあります。
メール誤送信対策の製品の機能について
実際に日本の製造業や、情報システム業を営んでいる企業の中には既に導入しているところも少なくありません。ではメール誤送信対策ができる製品にはどのような機能が搭載されているのでしょうか。
機能の一つとして挙げられるのが、人間工学を取り入れた送信確認画面で送信内容を再チェックしてから送信が可能になる機能です。基本的に企業においてはメールを複数の相手に送信する機会があります。一度に多くの送信先にメッセージを送ることができるので、情報共有の際の手間が少なくなります。しかし、一度に多くのメールアドレスを送信先として入力するので、そのメールアドレスの中には情報共有が必要ない人のアドレスが含まれていることもあります。できるだけ送信するメールアドレスの入力ミスを少なくするために、例えば初めて送信する相手には赤色で表示をさせて送信をする時に間違いがないか注意を促すことができます。
また、製品を導入することによって確認をしていない内容に関しては送信できないようにすることが可能になります。例えば添付ファイルなどです。これによって確認を促すことができるので、今までメール送信時の内容の見直しが定着しなかった企業でも、確認を促し社員に定着できる可能性があります。更に添付ファイルにパスワードを設定することも可能です。パスワードの設定に関しては自動化できるので、設定の手間などを削減することができます。このように製品導入を行うことで、メール誤送信の様々な対策を施すことができます。
メール誤送信対策ができる業者を利用しよう
メール誤送信対策ができる製品を導入する時には業者を利用し、利用する旨を伝えるのが一般的です。業者ではホームページなどでお客様の声を掲載して導入後にどのような利点を得ることができたのかを紹介しているとことも多くあります。もしどのような課題を解決できるのか明確に理解できなかったという人はお客様の声から情報を得ることで参考にできる可能性があります。
または業者のホームページから問い合わせすることも可能です。そのため、もし現在課題を抱えている企業は問い合わせフォームや電話相談などで、製品を導入すればどのような課題が解決できるのかをしっかりと確認して導入を決定することも可能です。