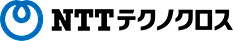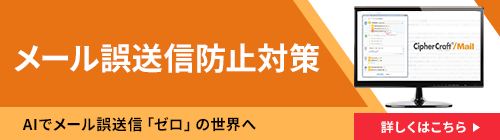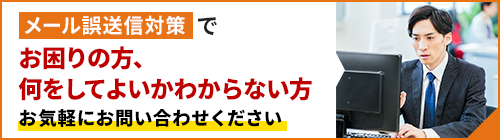Copyright © 2018-2025
NTT TechnoCross Corporation
ここに本文を書きます。
メールセキュリティのコラム
2025.03.11
【決定版】メール誤送信対策の全体像をわかりやすく解説
メール誤送信対策の全体像をわかりやすく解説 Topics

メールの誤送信対策をしないとどういう事故が起きてしまうのだろう。
メール誤送信対策についてどういう方法があるのか知りたい。
メール誤送信対策ツールの選び方はどうすればいいの?
情報漏洩事故に繋がるメール誤送信は、企業経営にとって非常に大きなリスク要因だと言えます。
実際に情報漏洩が起きた場合の影響は非常に広範囲になってきます。
・顧客の信頼喪失による売上減
・関係者への報告及びお詫び作業の発生
・多額の損害賠償や取引停止
・社会的な信頼の低下
・株価の低下
・風評被害
これらが、従業員のちょっとしたメールの誤操作から発生してしまうところが、メール誤送信の恐ろしいところです
企業経営に影響が出てしまう可能性があるからこそ、メール誤送信対策はしっかり行っておくべき施策だと言えるでしょう。
本記事では、メール誤送信によって引き起こされる事故、その対策、引き起こさないための予防策やメール誤送信対策ツールの選び方など、メール誤送信の全体をわかりやすく解説しました。
メール誤送信の対策をしないとリスクが高まる情報漏洩事故 Topics
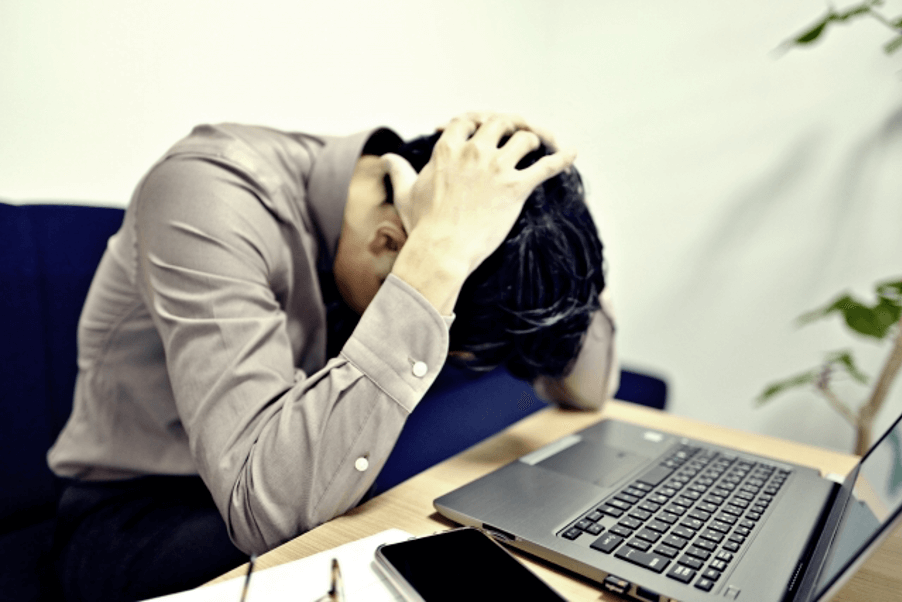
まずは、メール誤送信対策をしなかった場合に起きてしまう情報漏洩事故について、以下の2パターンに分けてご紹介をいたします。
・個人情報漏洩
・機密情報漏洩
それでは、それぞれ解説していきます。
個人情報漏洩
1つ目は、個人情報漏洩です。
個人情報というのは、生年月日や、住所、氏名などのほか、マイナンバー、クレジットカード情報、指紋などの身体的な情報まで個人を特定できる、個人に帰属するプライバシーに関わる情報のことを指します。
個人情報漏洩とは、自社サービスの利用者やイベント参加者のリスト、メールのアドレス帳など、企業が保有している社外の個人情報が外部に漏れることです。
インターネットの普及とともに、個人情報の取り扱いに対する社会的なルール作りが勧められました。
2005年から施行された個人情報保護法では、個人情報を扱う事業者が守るべき義務が明示されており、それらを違反し個人情報保護委員会からの改善命令に従わない場合は、罰則を科されます。
たった1通のメールの誤送信によって個人情報が外部に漏れてしまった場合であっても、立派な情報漏洩事故となってしまうため、個人情報の扱いは非常に慎重に行う必要があると言えます。
機密情報漏洩
2つ目は、機密情報漏洩です。
機密情報とは、企業が活動をする中で社外に公開していない情報のことを指します。
企業が健全な経済活動をするためには、自社の保有する重要な情報が他社に漏れることは絶対に避けるべきことです。
例えば、新規事業の企画書を提携先企業の担当者に送るつもりで、他社に誤ってメール送信してしまった場合などは、機密情報の漏えいに当たります。
個人情報と同様に、機密情報の漏洩も企業経営に大きな影響を与えるリスクがあるため、情報漏洩事故が起きないように対策をしっかり行う必要があると言えます。
対策すべきメール誤送信の発生状況 Topics
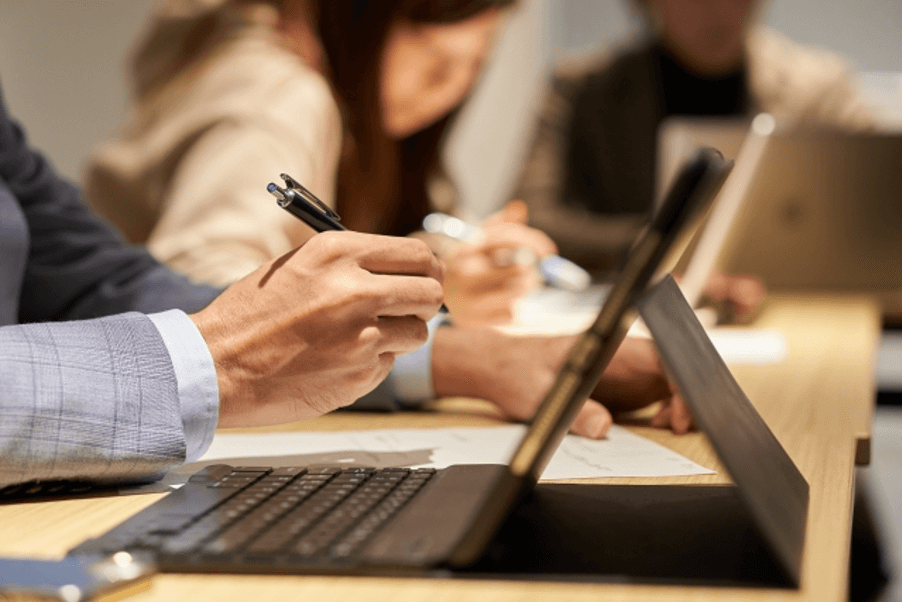
それでは次に、どういった状況でメール誤送信が発生するのかについてご紹介してきます。
情報漏洩の原因の大半は「ヒューマンエラー」といわれており、約40%がメールやFAX、郵便による「誤操作」であることが調査によりわかっています。
ここでは、以下の4つの発生状況について紹介します。
・メールの送付先を入力ミスした
・文章内容をミスした
・添付ファイルを間違えた
・セキュリティ運用ルールの対応漏れ
それでは、それぞれ簡単に解説をしていきます。
メールの送付先を入力ミスした
1つ目は、メールの送付先を入力ミスしたという状況です。
メール送信先を間違えるというミスは発生しやすい情報漏洩事故です。
例えば、同姓同名の違う人物にメールを送ってしまうといったことが起きます。
また、気をつけないといけないトラブルがBccを使ったメール送信です。
仕事で関係する社外の関係者に知っておいてもらうために「Bcc」でメールに入れたつもりが、Ccになっていた場合、それだけで情報漏洩になってしまう可能性があるのです。
メールアドレスは、姓名@社名.co.jp
のような構造になっている企業も多く、誤ってCcに入れただけで、意図しない社外の人に個人情報を漏らしてしまうことになります。
文章の内容をミスした
2つ目は、文章の内容をミスしたという状況です。
これは、メールが下書き状態でまだ未完成にも関わらず送ってしまったり、コピーして貼り付ける前に誤って送ってしまうというケースです。
送信先を入れた状態でメール文章を修正していて、誤って送信のショートカットキーを押してしまった際に意図せずメールが発送されてしまうことが、発生します。
意図しない内容を送信してしまうことで、本来伝えるべきではなかった機密情報を漏らしてしまうなどの問題に繋がる可能性があります。
添付ファイルを間違えた
3つ目は、添付ファイルを間違えたという状況です。
送るべき添付ファイルと違う添付ファイルを誤って送ってしまうということです。
ファイル名が似ていた、パソコン上でのファイル管理先が普段と異なっていたなど、誤った添付をしたことに気づかずに送ってしまうといったことで発生します。
ファイルの中に個人が特定できるような情報が含まれている場合は、機密情報の漏洩だけではなく個人情報の漏洩になってしまい、より大きな被害になってしまいます。
セキュリティ運用ルールの対応漏れ
4つ目は、セキュリティ運用ルールの対応が漏れたという状況です。
社内のセキュリティ運用ルールに記載があるにも関わらず、そのルールを認識しておらず、破ってしまうというケースが考えられます。
具体的には、CcやBccで社外の複数名に対して一斉送信をしてはいけない、といったルールがあっても、それを知らずに行ってしまうというようなケースです。
例えば、セミナー参加者に対してセミナー運営者からお礼のメールを送信する際に、社外の知らない人同士をToやCcに入れて一括でメールを送ってしまうというようなことを、新入社員などビジネス経験が浅い従業員の場合に、やってしまう可能性があります。
セミナーで同じ会場にいたとしても繋がっていない人もいますし、お互いに認識のない人同士をCcに入れて送ってしまうことで個人情報の漏洩になってしまいます。
セキュリティ運用ルールで一括送信禁止となっていたとしても、ルールを把握しておらず、うっかりToやCcで送ってしまうということが起きうるのです。
メール誤送信の発生原因を整理して対策しよう Topics
次に、メール誤送信の発生原因を整理する事で対策することについてご紹介していきます。
メール誤送信の発生原因としては主に以下の2つになります。
・人に依存する発生原因
・環境に依存する発生原因
それでは、それぞれを解説していきます。
人に依存する発生原因
1つ目は、人に依存する発生原因です。
これは、社員が注意散漫になっており、単純な作業ミスをしてしまったり、業務がマンネリ化して本来チェックすべき項目をつい忘れて作業をしてしまう、といった発生原因です。
また、トラブルが起きないように運用ルールを作ったにも関わらずその運用が徹底されなかったり、形骸化して現場でちゃんと運用がされないということも含まれます。
環境に依存する発生原因
2つ目は、環境に依存する発生原因です。
パソコンなどのハードウェアやネットワークの問題で、本来作業者が意図しない挙動を環境が起因して起こしてしまうという原因です。
例えば、パソコンが老朽化してエンターキーが潰れてしまっていて、メール作成時に意図せずにメール送信のボタンを押されてしまい、誤送信が行われてしまうといったことです。
メール誤送信が起きた場合の対策方法
次に、メール誤送信が起きた場合の対策方法についてご紹介をいたします。

メール誤送信を起こした後、2次的な被害が広がらないように、対策方法は事前に把握しておくべきでしょう。
謝罪をする
まずは、誤ってメールを送付してしまった先に対して、謝罪をする必要があります。
誤ったメールを送ってしまった宛先にメールで謝罪文を送ったり、場合によっては電話だったり直接訪問して謝罪に上がります。
謝罪とともに誤送信した内容については破棄するように依頼をするケースもあります。
原因を洗い出して再発防止策を考える
謝罪をしたのち、原因を洗い出して再発防止策を考えます。
同じ事が起きないよう運用ルールやメールシステムなどの仕組みを用意して対策をするとともに、改めてヒューマンエラーが発生しないように社内のセキュリティ意識を高めるといった対策もしましょう。
具体的な対策については、次の章でご紹介をしていきます。
メール誤送信を防ぐ4つの具体的な対策 Topics
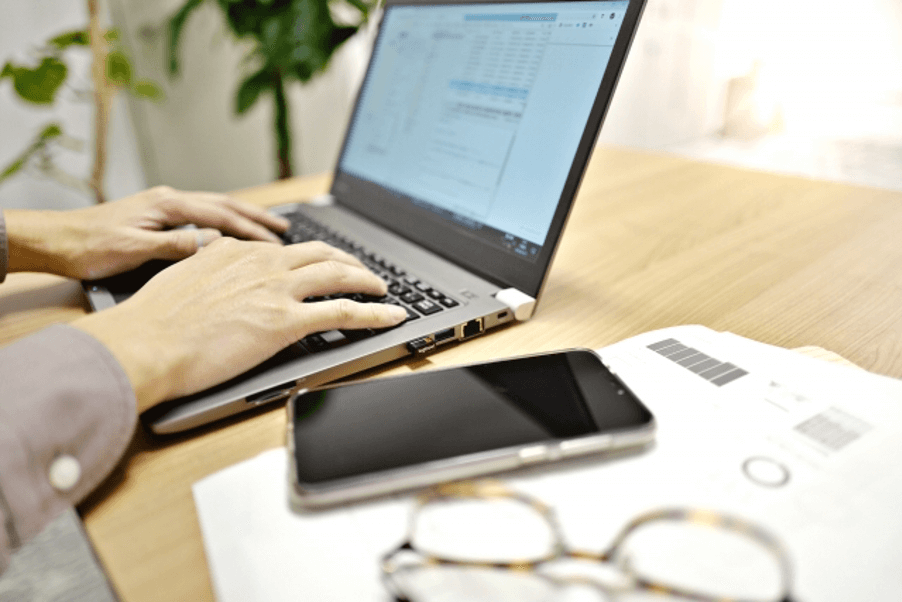
ここでは、メール誤送信を防ぐ4つの具体的な対策についてお話をしていきます。
・セキュリティの運用ルールを作る
・社員教育を徹底する
・送信予約を活用する
・メール誤送信防止ツールを活用する
それではそれぞれを見ていきましょう
セキュリティの運用ルールを作る
1つ目の対策は、セキュリティの運用ルールを作るということです。
ルールを決めておかないと従業員が各々の判断でメーラーの設定をしていまい、トラブルの火種になります。
セキュリティの運用ルールとしては、例えば以下のようなルールがあります。
・メールアドレスの予測入力機能をオフにする
・不要な連絡先をアドレス帳から削除しておく
・添付ファイルを暗号化する
・送信メール作成後、確認してから送信する
・社内関係者の入っているメーリングリストをCcに入れる
自社の状況に応じて、メールに対する社内ルールを決めておきましょう。
社員教育を徹底する
2つ目は、社員教育を徹底するということです。
メール誤送信は、その多くが人為的な作業ミスによって起きています。
メール送信をする際に、集中力が切れてしまい、複数の作業を同時にしている間にファイルを取り違えるなどといったことから、誤送信につながっていきます。
メールが会社にとって大きなリスクを内包する行為であり、毎回、緊張感をもって作業をするように定期的に啓発をすることも重要です。
また、会社で策定したメール運用ルールを改めて認識させるなど、メール取扱に関する社内教育を徹底することも重要な対策です。
送信予約を活用する
3つ目は、送信予約を活用するということです。
メールは一度送信してしまうと取り消すことができないため、送信前の確認作業は誤送信に対する重要な対策の1つです。
予約送信機能が付いているメーラーであれば、いきなり送信するのではなく、少し先の時間に送信予約して、その間に改めて誤りがないかチェックすることは有効な誤送信対策になります。
添付ファイルの誤りがないか、送信先に誤りがないかといった点を見直しして、情報漏洩のリスクを排除してから送信する事ができます。
メール誤送信防止ツールを活用する
4つ目は、メール誤送信防止ツールを活用するということです。
ここまで紹介した3つの対策はどれも、社員自身が意識をしたり実際に作業をしないことには実行されない、最終的に社員に依存した対策でした。
一方で、メール誤送信防止ツールは、社員自身のメール送信に対する行動をシステムによって制御する事ができるので、企業側が強制力を効かせて実行をすることができる施策です。
メール誤送信対策ツールには様々な機能がありますので、次の章で主な特徴をピックアップして解説します。
メール誤送信対策ツールの主な特徴 Topics
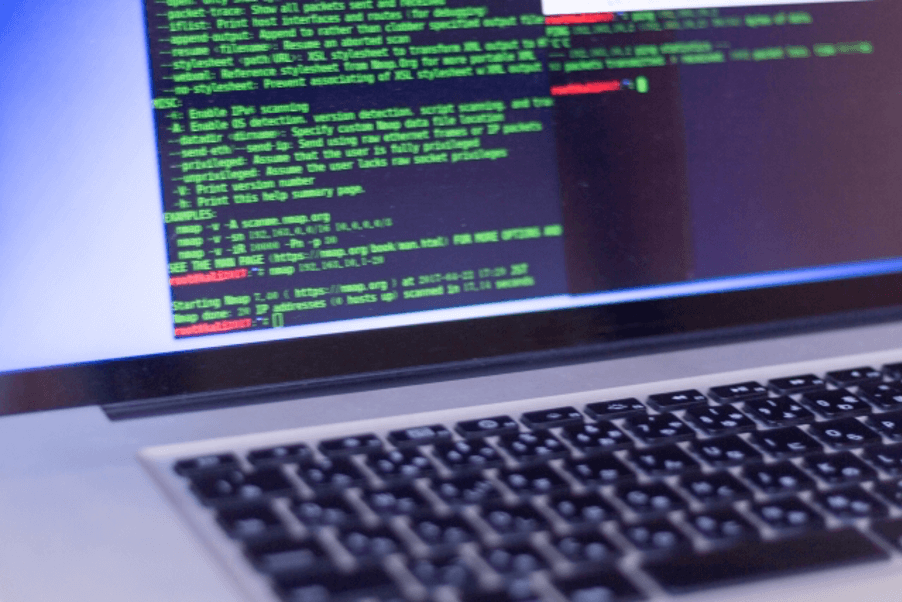
ここではメール誤送信対策ツールについて特徴を詳しく解説をしていきます。
今回、主要な特徴として以下の3つをピックアップして紹介します。
・ダブルチェック後に送付可能にする
・添付ファイルを自動的に暗号化する
・社内同報なしでのメール送付を不可にする
それでは、一つ一つ見ていきましょう。
ダブルチェック後に送付可能にする
1つ目の主な特徴は、ダブルチェック後に送付可能にできるということです。
通常、メールを送信する場合は即送信されるのが初期設定ですが、送信をしても別の人がチェックし、承認をしないと送信されないという仕組みを実装することも可能です。
送信前のメールをダブルチェックにすることは、情報漏洩対策の観点からは非常に有効な手段といえます。
添付ファイルを自動的に暗号化する
2つ目の主な特徴は、添付ファイルを自動的に暗号化できるということです。
添付ファイルの暗号化によって、添付ファイルとするドキュメントを事前に暗号化することで、選択ミスをした場合も情報漏洩が防げます。
パスワードなどは、別の通信手段等を用いて相手に伝えることが必要になりますが、個人情報や機密情報を守れる有効な手段と言えます。
暗号化をすることで、添付ファイルが漏れても中身を読めない状況にすることで、情報漏洩事故を防ぐことができます。
添付ファイルの暗号化を必ず行うようにすることで、万が一の時でも、情報漏洩事故にならないように対策することができます。
社内同報なしでのメール送付を不可にする
3つ目の主な特徴は、社内同報なしでのメール送付をできないようにするということです。
CcやBccの宛先に必ず、指定の社内メンバーやメーリングリストを入れないと送信できないという設定にすることで、誤送信が起きてしまった場合の発見をスピーディに行えます。
また、自分の送信するメールが必ず社内の他のメンバーにもチェックされるという状況自体が、メール送信に対する緊張感・集中力を高めて、ミスが起きにくくなるという効果も期待できます。
メール誤送信防止ツールの選び方 Topics
最後にメール誤送信防止ツールの選び方について、3つのポイントを解説していきます。
・機能面での充実
・従業員視点での使いやすさ
・管理視点での使いやすさ
それでは、それぞれ解説してきます。
機能面での充実
1つ目のポイントは、機能面での充実です。
メール誤送信防止ツールは、色々な企業が開発をしていますが、それぞれのメーカーごとに実装されている機能が異なっています。
また、スマートフォンに対応していないものや、パソコンでもWindowsしか対応していないものなど、使用できる環境が異なります。
自社の状況とニーズに合わせて、必要な機能が揃ったツールかどうか見極めましょう。
従業員視点での使いやすさ
2つ目のポイントは、従業員視点での使いやすさです。
メール誤送信防止ツールの導入は、従業員のメール作成・送信作業の工程を増やすことになります。
ツールによって業務のパフォーマンスに影響が出ないように、なるべく負荷の少ないツールや迷わず使えるツールを選ぶべきだと言えます。
デモやトライアルを通じて実際にツールを触ってみて、使いやすさを確認しましょう。
管理視点での使いやすさ
3つ目のポイントは、管理視点での使いやすさです。
メール誤送信防止ツールは導入時に詳細な設定をし、従業員の端末で利用できるように動作環境を確認・用意する必要があります。
また、運用が始まってからも定期的に誤送信が起きていないかチェックをし、パソコンの入れ替えやOSのバージョンアップなどインフラが変わる場合の動作確認など、運用業務も定常的に発生します。
管理側の業務がスムーズに迷わず行えるツールかどうか、管理画面の使いやすさも確認をしましょう。
さらに、導入実績が充実している製品の方が改善が行き届いており、活用ノウハウも蓄積されていることが多いため、過去実績もチェックしましょう。
まとめ Topics

本記事では、メールの誤送信についてその状況や原因、対策、ツールまで、幅広くご紹介をしました。
情報漏洩事故の発生件数はIT技術の発展と共に年々増加しています。
メールの誤送信は、社員が少し注意を怠るだけでも発生してしまう一方で、場合によっては企業経営へ大きな悪影響を与える可能性があるため、軽視できないリスク要因と言えます。
自社が情報漏洩事故を起こさないためにも、改めてメール誤送信対策を再確認しましょう。