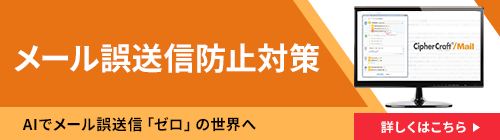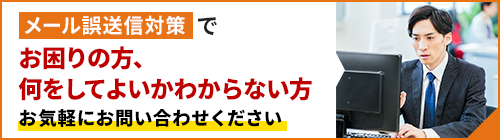ここに本文を書きます。
メールセキュリティのコラム
2025.03.13
メール誤送信のリスクと添付ファイルにパスワードをかける対策
メール誤送信のリスクと添付ファイルにパスワードをかける対策


メール誤送信のリスクについて
メールはプライベートだけでなく、企業の中にも利用している人が多いです。その理由は利便性が高いからです。例えば差出人を複数設定することができるので、同時に数多くのクライアントに一斉送信することができます。そのため、伝達の手間を少なくすることが可能です。また、受信した相手は内容を見返すことができます。特に企業ではクライアントからの要求を受けることがあります。要求の内容が複数ある場合、電話でそのような内容を聞くと最後まで要件を正確に伝えることが難しいです。要件が伝わっていないとクライアントに迷惑をかける可能性があります。メールであれば見返すことができるので、伝えられた内容を忘れてしまっても受信ボックスを開けて後で見返すことで内容を再確認することができます。
このように様々な利点がありますが、使い方を間違えると企業はリスクを背負うことになることも事実です。リスクは誤送信によって発生します。基本的に企業では様々なクライアントなどにメールをする機会が多いです。また、共同でプロジェクトを進めることもあるので、協力してプロジェクトを行っている企業の社員に情報を伝達しなければならない時もあります。対応する人の数が多いので、誤って送信先を間違えて送ってしまう可能性があります。企業が送信する内容は外部に漏れると困るケースもあるので、誤送信によってリスクを受けることがあります。ではリスクにはどのようなものを挙げることができるのでしょうか。
リスクの一つとして挙げられるのが顧客からの信頼の低下です。信頼が低下すれば当然その企業が提供するサービスなどを利用してもらうことができなくなるので、売上の低下に繋がる危険性もあります。その他にもブランドイメージのダウンを挙げることができます。特に商品開発をしている企業では自社ブランドで何かの商品を販売することもありますが、誤送信により社会的な信頼の低下にともなってブランドイメージが低下してしまう可能性もあります。
このように誤送信によるリスクは複数挙げることができるため、企業の中には誤送信を防止する目的で誤送信防止の製品の導入をしている人も多いです。この製品を導入することでこれらのリスクを少なくすることができ、社員のメール送信によって企業が信頼を失ったり、ブランドイメージがダウンしたりしてしまわないような対策を施すことができます。
メール誤送信防止製品の機能について知る
実際にメール誤送信防止製品には様々な機能が搭載されていて、機能を知ることで会社が導入するべき製品かどうか判断することができます。
機能の一つとして挙げられるのが添付ファイルにパスワードをかけられることです。添付ファイルを普段から使った顧客とやり取りをする企業も多いです。例えば請求書や依頼書などをを添付すればメールに記載しなくてもファイルを添付するだけなので、送信の手間を少なくすることも可能です。しかし、請求書や依頼書は比較的重要な書類になるので、誤送信をしてしまうと企業が受けるダメージは少なくないでしょう。製品を導入すれば自動で添付ファイルにパスワードをかけることができるので、誤って送信してしまった時も相手は開封できず情報漏えいを未然に防ぐことができる可能性があります。
管理者の中には添付ファイル一つ一つにパスワードをかければそのような製品を導入しなくても対策ができるのではないかと考える人もいますが、社員の中で定着しない可能性があります。定着しなければ社員の中にはパスワードをかけずに添付ファイルを送信してしまう人も多くなるので、結果的に情報漏えいを防止することができなくなる可能性があります。製品を導入すれば自動で添付ファイルにパスワードをかけることができるので、面倒だと思う社員が少なくなることが期待できます。同時に添付ファイルのパスワード化が社内で定着させることができるでしょう。
メール誤送信が防止できる製品の選び方のポイント
現在ではメール誤送信を防止できる製品が数多く販売されているので、製品選びに躊躇する人も少なくありません。選び方のポイントとしては使いやすい製品であるかどうかです。使いにくい製品を導入すれば、その製品に慣れるまでに時間がかかるので業務非効率化が懸念されます。特に企業の中にはメールのやり取りが多いところもあるので、使いにくいと残業などをしなければならない社員も増えることが予想されます。まずは使いやすさを検討してみましょう。
その他のポイントとしては様々な環境に対応することができるかどうかです。様々な環境に対応することができれば多くの企業が製品の導入を行うことができる可能性があります。選ぶ際には導入実績などの確認もしましょう。導入実績が多ければその分安心して利用できると考える人も多いです。実際に数多くの企業に導入して誤送信をしないようにサポートしている製品も少なくありません。