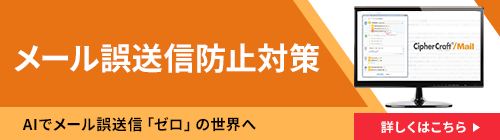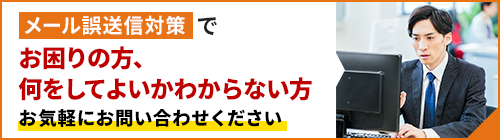ここに本文を書きます。
メールセキュリティのコラム
2025.03.13
相手とメールの送受信を行う前に、セキュリティ対策を万全に
相手とメールの送受信を行う前に、セキュリティ対策を万全に

メールのセキュリティ対策が、コンピューターウイルスの感染防止に繋がります
迷惑メールやコンピューターウイルスの対策を万全にしたいと考えている企業も多いでしょう。大量の迷惑メールが届いてしまうこと自体、対応が非常に面倒であり、従業員への負担が増しますし、重要なメールが埋もれてしまうといったことも考えられます。中には、コンピューターウイルスが付加されている危険なものもあります。
添付ファイルを開いただけでウイルスにかかってしまうものまで存在しており、従業員がうっかり添付されたファイルを開いてしまい、会社全体のネットワーク環境がおかしくなってしまうという最悪のケースもあり得ます。コンピューターウイルスは厄介なことに、一度感染してしまうと、修復することが難しく、素人ではお手上げ状態になりがちです。迷惑メールによるさまざまな弊害は、パソコンを使用する機会が多い企業や、多くの顧客や関係組織とネットワークでつながっている企業にとっては死活問題でしょう。
迷惑メールの大量受信を防ぐために、またコンピューターウイルス感染のリスクを減らすために、万全のセキュリティ対策が必要です。コンピューターウイルスにかかってからでは遅くなってしまいます。事前の対策が重要ですから、「怪しいファイルを開かなければ大丈夫、うちのパソコンはウイルスになんてかからないだろう」という考えはあまり好ましくありません。
最近では、情報通信ネットワークに関する各種サービスの提供を行っている会社が、フィルターシステムや、ウイルス対策ツールといったセキュリティ対策を各企業に提供しています。対策をまだしていない、セキュリティ対策をより一層強化したいという企業は、後悔する前に今すぐ行動することが大切です。
メールのセキュリティ対策は、受信する際はもちろん送信する際も有益です
会社や個人のパソコンを守る、情報通信ネットワーク関係会社が提供しているセキュリティ対策にはどのようなものがあるのでしょう。近頃、大学や通信教育の現場でもよく見受けられるログオンパスワード付スクリーンセーバーや、ウィルス対策ツール、ウイルス定義ファイルの自動更新システム等はいまやお馴染みで、ご存知の方も多いでしょう。
形を変えるコンピューターウイルスに対して有効的な、ウィルス定義ファイルを最新化できるシステムもありますし、送受信メールサーバにウイルス対策を導入することで、ウイルス感染をチェックしたりすることもできます。最近のセキュリティ対策としておすすめしたいのは標的型メール対策と、誤送信防止、自動暗号化システムです。攻撃パターンが増加、巧妙化している迷惑メールに対し、ウイルスが付加されている疑いがあるものを自動的に隔離し、受信者に注意喚起の画面を表示します。
また、定期的な標的型攻撃の訓練により受信者の標的型攻撃に対する意識を高め、攻撃を未然に防止します。分かりやすく機能を説明すると、ウイルスが添付されている可能性のあるものが届いた際に受信者に警告を出すことができる、不審な内容のものを自動で隔離できる、訓練用の疑似メールを送り受信者に注意を促すことができる、というものです。受信する側の対策はもちろん重要ですが、自分の会社からも相手方にとって迷惑となるような誤送信や、うっかりでは済まされないような情報漏洩は避けたいところです。
そんな時に利用してほしいセキュリティ対策が、誤送信防止・自動暗号化システムです。送信内容について再度確認を促すツールが表示されるシステム、そして送信時の指定したルールによって添付ファイルを暗号化したり、上司の承認がなければ送信できないようにするなど送信時のルール設定やシステムでの制御が可能です。受信する際の安全性の確保だけでなく、送信する際の安全性にも配慮して初めて万全のセキュリティ対策と言えます。
高い費用対効果を発揮するメールセキュリティ対策
情報のセキュリティ対策は実際に大手企業、航空会社、金融機関といったさまざまな分野で導入されており、コンピューターウイルス感染や情報漏洩といった弊害のリスクを減らし、高い費用対効果を発揮しています。
セキュリティ対策を導入している企業には、いろいろな実益がもたらされています。受信する際にしっかりとセキュリティ対策をしていれば、社員が受信前に迷惑メールかそうでないかを判断することできます。その結果、情報システム部への問い合わせを大幅に削減することができるため、従業員の負担を軽減することに繋がります。
日常業務で発生する情報漏洩を未然に防止できる誤送信対策を導入していれば、従業員が安心して相手先との取引を行うことができ、業績アップに繋がることでしょう。受信対策と誤送信対策は併用することもでき、併用したほうが効率的です。まだセキュリティ対策を導入できていない方や、受信する際の対策しかしていないといった方は、情報通信ネットワーク各種サービスの提供元に問い合わせてみると良いでしょう。