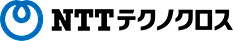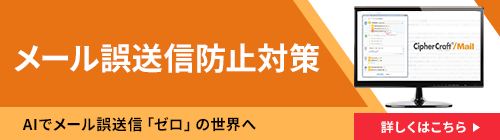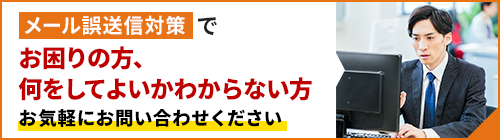Copyright © 2018-2025
NTT TechnoCross Corporation
ここに本文を書きます。
メールセキュリティのコラム
2025.03.13
メールセキュリティの脅威と対策を徹底解説

ビジネスでは当たり前に使っているメールですが、そのメールにセキュリティリスクがあることをご存じでしょうか。
しっかりと対策しなければ情報漏洩につながり社会的信頼を損なう可能性が高くなります。最近では手口が巧妙化しており、従業員への教育だけでは不十分です。
本記事ではメールに潜むセキュリティリスクとその対策について紹介していきます。
メールセキュリティの必要性
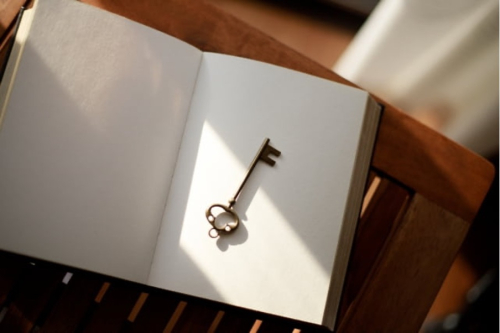
ビジネスでやり取りされるメールには個人情報や機密情報が含まれることが多く、マルウェアの感染や標的型攻撃のターゲットにされ、そうした情報が盗まれる被害が後を絶ちません。
最近では手口も巧妙になっており、従業員1人ひとりの意識に任せるだけでは、気づかぬうちに攻撃を受けて情報漏洩といったトラブルに見舞われてしまいます。
そのトラブルを避けるためにも、メールのセキュリティ対策が必要になってきます。
メールに潜むセキュリティの脅威

メールを使ったサイバー攻撃といっても、具体的なものがないとなかなかイメージできないですよね。
そこでこの章では、メールに潜むセキュリティの脅威を5つ紹介します。
メールの誤送信
一つ目はメールの誤送信です。
これは攻撃を受けるより人的ミスによる場合が多いですが、セキュリティの側面から見た場合、外すことができないセキュリティリスクです。
メールアドレスの入力ミスや添付するファイル間違えなど、メールの誤送信によって情報漏洩を引き起こす大きな原因になります。
例えば、A社とのやり取りで使っていた機密情報の入った資料を誤ってB社に送付してしまったなど考えられます。
また漏洩した情報の内容によっては、訴訟問題にまで発展する可能性もあり、メールの誤送信は企業経営の大きなリスクになり得ます。
マルウェアの感染
2つ目はマルウェアの感染です。
マルウェアとは有害な動作を行うために作成された悪意あるソフトウェアです。パソコンの内部情報を勝手にメール送信したり、ユーザーのキーボード操作をそのまま外部に送信するようなものもあります。
攻撃者はこういったマルウェアを添付ファイルやURLに仕込んでメールを送ってきます。
何気なく開いてクリックしたらマルウェアに感染し、気づかぬうちに個人情報や機密情報、業務システムのパスワードなど、情報が流出してしまうといったことが考えられます。
フィッシング詐欺
フィッシング詐欺とは、有名企業や銀行を装ったメールを送信し、本物そっくりの偽サイトに誘導してクレジット番号や個人情報を取得しようとする詐欺のことです。
フィッシング詐欺に遭い、カードを不正利用されてしまった事例もあります。
テレワーク中に勤務先の電子メールアドレスに「クレジットカード請求額のご連絡」という件名の電子メールが届いた。
所有しているクレジットカードと同じ会社からの電子メールだったが、最近カードで買い物をしていないので誤請求かどうか確認しようと思い、電子メール本文に示されたリンク先にアクセスし、指示されたとおりにカード番号や有効期限等の情報を入力したところ、後日カードの不正利用をされてしまった。
冷静に考えてみると、クレジットカード会社には勤務先の電子メールアドレスを伝えていなかったので、不審メールと気付くことはできたはずだった。
引用:総務省 テレワークセキュリティガイドライン第4版 41ページ
このようなかたちで、なりすましてユーザーから情報を抜き取る悪質な行為が行われているため、信頼できる情報なのか注意して対応をする必要があります。
標的型攻撃
標的型攻撃とは、特定の組織や人に絞っておこなうサイバー攻撃です。
ターゲットの知り合いや取引先を装い、悪意あるファイルを送りつけてマルウェアに感染させたり、偽サイトに誘導して個人情報を引き出したりします。
標的型攻撃の厄介なところは、攻撃対象を定めてその対象から個人情報や企業の機密情報を搾取する目的で行われることです。
万一、攻撃を受けた際は、何かしらの情報が流出し企業として大きな損失がでる可能性が高いと言えます。
メールの盗聴
メールは暗号化して送信をしなければ、相手方に届くまでの間で「平文」でやり取りされる区間があり、悪意を持った第三者によってメールの中身が見られる恐れがあります。
もし、メールに個人情報や機密情報が含まれていた場合、その情報が誰かの手に渡って、悪用されてしまうリスクとなるでしょう。
「あて先に記された人以外はその内容を見られない」と思いがちですが、インターネットを介してやり取りされる以上、その考えは捨てるべきと言えるでしょう。
悪意を持った第三者は常に情報を狙っているため油断は禁物です。
様々なメールセキュリティの対策

ビジネスで当たり前に使っているメールですが、悪意を持った第三者が攻撃の対象として日々狙っています。
ひとたびマルウェアやフィッシング詐欺の被害にあってしまうと、企業として大きな被害がでることは間違いないでしょう。場合によっては加害者として訴えられる可能性もあります。
そうならないためにもメールのセキュリティ対策が必須です。ここでは、そんなメールセキュリティ対策を紹介していきます。
ウィルス対策ソフト
すでに多くの企業で導入されていますが、マルウェアに気づくためにはウィルス対策ソフトが一番効果的です。もしマルウェアに感染してしまったとしても、ウィルス対策ソフトが自動で駆除してくれます。
メールセキュリティ対策に限らず、不審なサイトへのアクセス警告やブロック機能も搭載されており、あらゆるセキュリティリスクに対応しています。
日々アップデートされるマルウェア情報に対応したパターンファイルも更新されているので安心です。
スパムメールの設定をする
不特定多数に送られている迷惑メールの中には、本文中のURLや添付ファイルをクリックするとパソコンが乗っ取られたりマルウェアに感染してしまうものが紛れ込んでいる可能性があります。
誤ってクリックしないためにも、スパムメールの設定をすることが大切です。
スパムメール設定は2つの方法があります。
- ・メールサーバー側での対策
- ・ユーザー側での対策
メールサーバー側というのはメールサービスを提供している業者が行っている対策です。これまでの膨大なデータからスパムメールの傾向を分析し、似たようなメールを自動で処理するといった機能を提供しています。
ユーザー側の対策は、メールツールで特定のユーザーから送られてくるメールを拒否したり、スパムメールフォルダに自動的に振り分けるといった設定を行うことです。
なかには学習機能が備わっているツールもあり、そうしたツールでは数を重ねるほど振り分けの精度をあげていくことも可能です。
メールの無害化
メールの無害化とは、メールをより安全にするために本文のURLや添付ファイルのリンクを無効にするものです。
これによって誤ってクリックすることを防げ、人的ミスによるマルウェアの感染リスクを軽減できます。
一方で、無害化することでオリジナルのメールと違うメールになり困ることも出てきます。そうした場合は、システムの管理者などに申請してメールサーバー上に残っているオリジナルメールを提供してもらいましょう。
メールの暗号化
メールそのものを暗号化することも大切です。
メールといってもインターネットを介してやり取りされているので、暗号化してないメールは悪意をもった第三者に覗き見される可能性が高くなります。
メールを暗号化することで、覗き見防止になるほか、改ざんやなりすましの対策ができます。
メール誤送信対策
メール誤送信の多くは、送信者の操作ミスや不注意で起こります。送信者が慎重になることで防げることがほとんどですが、なかなか減っていないのが現状です。
件数も多く、誤送信対策を目的としたツールがあります。
誤送信が発生してしまったら関係各所への謝罪や場合によってはメール削除の依頼が必要になります。
そうならないためにもツールを導入して、誤送信を減らすことが大切です。
メールのセキュリティ対策は企業にとって必要不可欠

以上、メールセキュリティの内容とその対策について紹介してきました。
最近のメールを使ったサイバー攻撃は手口が巧妙になり、ターゲットを絞る標的型攻撃が多いです。マルウェアやフィッシング詐欺等で特定の個人情報や企業の機密情報を狙っています。
ひとたびサイバー攻撃から情報流出となってしまったら、その被害の大きさははかり知れません。場合によっては加害者となることもあり、取引先、ひいては世間にただいな損害を与えてしまう可能性もあるでしょう。
そのような事態を避けるためにも、メールのサイバー攻撃から守るメールセキュリティ対策が大切になります。
弊社では、メール誤送信防止や標的型メール対策に対応するサービスを提供しております。添付ファイルの暗号化や電子署名の付与、上司承認後にメールを送信したりする機能があります。
メールセキュリティ対策を効率的に行うなら、ツールが最適です。弊社のCipherCraft/Mailシリーズならお客様の環境に合わせたご提案をさせていただきます。無料評価版もあるのでぜひお問い合わせください。